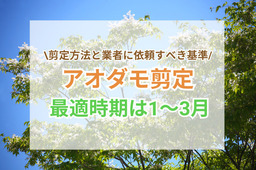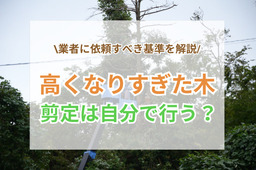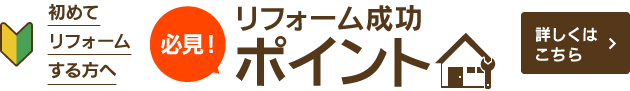ゴムの木剪定の最適な時期

ゴムの木の剪定は、時期を間違えると株を弱らせてしまうこともあり、適切なタイミングを知ることが、剪定を成功させる大切な鍵になります。
剪定に最適な時期は年に2回あり、それぞれにメリットがありますが、絶対に避けるべき時期もあるため、正しい知識を身につけてゴムの木の健やかな成長をサポートしましょう。
春から初夏(3〜7月)が狙い目
ゴムの木の剪定に最も適した時期は、春から初夏にかけての3〜7月とされています。
この期間は気温が安定してゴムの木の成長期にあたるため、剪定後の回復が比較的早いのが特徴です。
成長期だからこそ失敗が少ない
春から初夏は新芽が活発に伸びる時期なので、剪定によるダメージからの回復がスムーズに進みます。
切り口の治りも早く、病原菌が侵入するリスクを最小限に抑えられるのも大きなメリットです。
特に気温が20℃前後になる過ごしやすい季節は失敗しにくい傾向があり、初心者の方でも取り組みやすい時期といえるでしょう。
7月以降は避けるのが賢明
7月の後半から8月にかけての真夏は、厳しい暑さによるストレスでゴムの木が弱りやすくなります。
この時期の剪定は株に大きな負担をかける恐れがあるため、遅くとも7月上旬までには作業を終えるのが理想的です。
9〜10月の剪定でもOK
春が剪定のベストシーズンとして知られていますが、実は秋の9〜10月も剪定に適した時期です。
この頃は真夏の暑さが和らぎ、株が元気を取り戻して気温も安定するため、安心して剪定できます。
秋に剪定する一番のメリットは、冬が来る前に切り口をしっかり治す時間を確保できる点です。
ゴムの木は切り口から出る白い樹液が固まることで傷を保護しますが、本格的な寒さが来る前に回復を終えられれば、株が弱る心配もありません。
ただし、気温には注意が必要です。最低気温が15℃を下回る前に、遅くとも10月中旬までには剪定を済ませるようにしましょう。
冬は休眠期なので避ける
冬のゴムの木は成長が緩やかになる休眠期に入るため、剪定は避けるのが安全です。
熱帯原産のゴムの木は寒さに弱く、冬に剪定すると切り口の回復が遅れ、病気に感染したり枯れたりするリスクが高まります。
特に11~2月の寒い時期は木のエネルギーが低下しているので、剪定を控えるのが賢明です。
どんなに枝が伸びていても、回復力の高い春まで待つことが、ゴムの木を元気に保つ大切なポイントです。
\専門業者に相談したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
剪定の基本的な考え方
ゴムの木が大きくなりすぎてお困りの方も多いのではないでしょうか。
適切な剪定を行えば、理想の高さでバランスの取れた美しい樹形に整えられます。
高さ調整
ゴムの木の高さを調整する際は、まず「どこまでの高さにしたいか」を決めてから作業を始めましょう。
切る位置は、目標の高さより少し上にある節のすぐ上が基本です。
節を1〜2つ残し、外側に向いている芽の上を目安に斜め45度でカットすると、新芽が出やすくなり樹形が美しく整います。
段階的な剪定で株への負担を軽減
主幹や太い枝を一度にバッサリと切るのは避けてください。
株への負担が大きく、枯れ込んでしまう原因になりかねません。
特に大きく育ったゴムの木の場合は、数回に分けて少しずつ短くしていくことが大切です。
新芽の管理で理想の樹形へ
切り戻した後は、早ければ2〜3週間ほどで新しい芽が複数出てきます。
枝の節にある膨らみから新芽が伸びてくるので、伸ばしたい方向の芽を1〜2本だけ残し、不要な芽は早めに摘み取りましょう。
この一手間を加えることで、バランスの取れた美しい枝分かれを作ることができます。
枝分かれ
ゴムの木は、何もしないと上へ上へと伸びてしまい、なかなか枝分かれしにくい性質があります。
バランスのよい樹形にするには、主幹の先端をカットして脇から新しい芽が出るように促してあげましょう。
枝分かれさせたい位置の5cmほど上を目安に、切れ味のよいハサミで切ります。
新しい芽は、今ある葉の付け根や、葉が落ちた跡の少し上あたりから出てきますよ。
剪定から1か月ほどで複数の新芽が出てきたら、伸ばしたい方向の芽を2〜3本選びましょう。
内向きに伸びる芽や、他の枝と重なりそうな芽は早めに摘み取るのがポイントです。
左右対称になるか、放射状に広がるかなど、全体のバランスを見ながら残す芽を決めると、理想の美しい樹形に仕立てられます。
仕立て直し
ゴムの木を長く育てていると、下のほうの葉が落ちて幹だけがひょろっと伸びた姿になることがありますよね。
葉がなくなった部分から再び葉が生えることはほとんどないため、見た目のバランスが悪くなってしまいがちです。
そんなときは、思い切って短く切り戻す「仕立て直し」で、美しい樹形を取り戻しましょう。
カットする位置は、必ず「節」の少し上がポイントです。
節は幹に入っている横線のことで、ここから新しい芽が出てきます。理想の高さまで、大胆にカットしてもほぼ問題ないでしょう。
切り戻した後は、いくつかの脇芽が出てきます。
すべての芽を育てると形が乱れてしまうので、バランスのよい位置にある2〜3本を選んで育てましょう。
内向きの芽や重なりそうな芽は取り除き、全体がこんもりと茂るように整えれば、また素敵な姿のゴムの木を楽しめます。
\専門業者に相談したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
剪定の注意点
ゴムの木の剪定を成功させるには、作業後の適切な処理と安全対策が欠かせません。
特に大きな切り口のケアは、植物の健康を左右する重要なポイント。
これらの注意点をしっかり押さえて、安全で効果的な剪定を行いましょう。
切り口から出る白い樹液の対処法
ゴムの木を剪定すると、切り口から白い樹液が出てきます。
これはラテックスという天然ゴムの成分で、空気に触れると固まる性質があります。
この樹液には、かぶれなどを引き起こす可能性のある成分が含まれているため、直接肌に触れないよう注意が必要です。
作業の際は、手袋を着用しましょう。
切り口から垂れる樹液は、床や家具を汚さないよう、清潔なティッシュなどを2〜3分当てて吸い取ります。
樹液はやがて自然に固まり、切り口を保護するフタの役割を果たしてくれるので、すべてを完全に拭き取る必要はありません。
周りに付いた余分な樹液だけをきれいに拭き取っておきましょう。
樹液によるかぶれ対策に手袋は必須
前述の通り、ゴムの木の樹液に触れるとかぶれてしまうことがあるため、剪定作業には手袋を着用することをおすすめします。
特に肌が敏感な方やアレルギーが心配な方は、ゴム手袋や園芸用の厚手の手袋を選ぶとより安心です。
樹液が飛び散ることもあるので、長袖の服を着て肌の露出を減らすことも大切なポイントになります。
万が一、樹液が肌や衣服に付いてしまった場合の対処法を次にまとめました。
|
|
作業が終わったら、手袋をつけたまま水洗いし、その後しっかりと手を洗って樹液を完全に落とすように心がけましょう。
大きな切り口は清潔にして管理する
太い枝を切った後の切り口は、病原菌が入り込むリスクがあるため、少し丁寧にケアしてあげましょう。
切り口に市販の癒合剤を薄く塗っておくと、病気の侵入や枯れ込みを防ぐのに役立ちます。
癒合剤を塗るタイミングは、白い樹液が完全に止まってからが基本です。
もし切り口の周りがささくれていたら、清潔なカッターなどで滑らかに整えてから塗布すると効果的です。
また、剪定後の管理も大切です。切り口が乾くまでは雨に当たらないようにし、水やりも少し控えめにするとよいでしょう。
このような一手間が、ゴムの木を病気から守り、元気に育てることにつながります。
\専門業者に相談したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
ゴムの木の剪定はコツをつかめば難しくない
ゴムの木の剪定は、ポイントさえ押さえれば、初心者の方でも簡単に取り組みやすくなるでしょう。
回復力の高い成長期(春〜初夏や秋)を選び、清潔なハサミを使って理想の樹形をイメージしながら作業することが成功の秘訣です。
剪定後は、樹液の処理や切り口のケアを丁寧に行い、ゴムの木が元気に回復するのを見守ってあげましょう。
この記事で紹介した方法を参考に、ぜひご自宅のゴムの木を、より美しく健康的な姿に整えてみてくださいね。
\専門業者に相談したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
こちらの記事もおすすめ♪
>> 石灰でドクダミ駆除

 リショップナビは3つの安心を提供しています!
リショップナビは3つの安心を提供しています!
-

ご希望にあった会社をご紹介!
お住まいの地域に近く・ご希望のリフォーム箇所に対応が可能という基準を元に、厳選した会社をご紹介。可能な限り、ご要望にお応えできるように対応致します。
-

しつこい営業電話はありません!
紹介する会社は、最大で5社まで。また、連絡を希望する時間帯をお伝え頂ければ、しつこい営業電話をすることはありません。
-

見積もり後のフォローも致します
ご紹介後にご不明点や依頼を断りたい会社がある場合も、お気軽にご連絡ください。弊社から各会社へのご連絡も可能となっております。


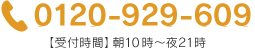
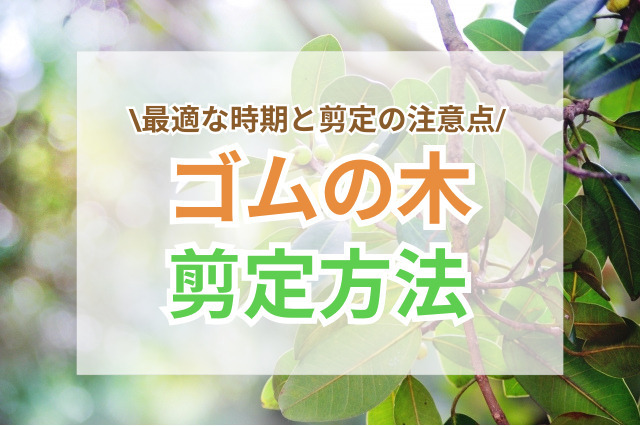
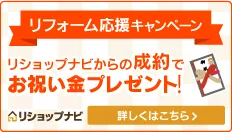

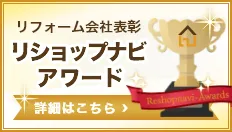
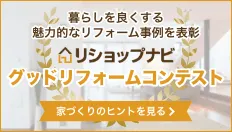

 ピックアップ記事
ピックアップ記事



 庭・ガーデニングリフォームのポイント
庭・ガーデニングリフォームのポイント
 豊富なリフォーム事例を公開中!
豊富なリフォーム事例を公開中!
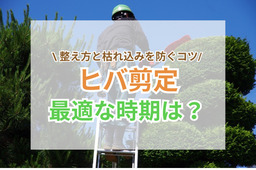 ヒバの剪定時期と整え方|枯れ込みを防ぐコ...
ヒバの剪定時期と整え方|枯れ込みを防ぐコ...
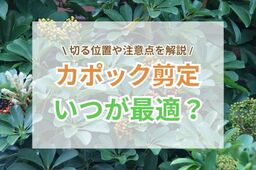 カポック剪定|最適な時期・切る位置や注意...
カポック剪定|最適な時期・切る位置や注意...
 キウイの剪定の最適な時期は冬と夏?|実を...
キウイの剪定の最適な時期は冬と夏?|実を...
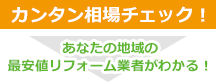
 庭・ガーデニングのおすすめ記事
庭・ガーデニングのおすすめ記事