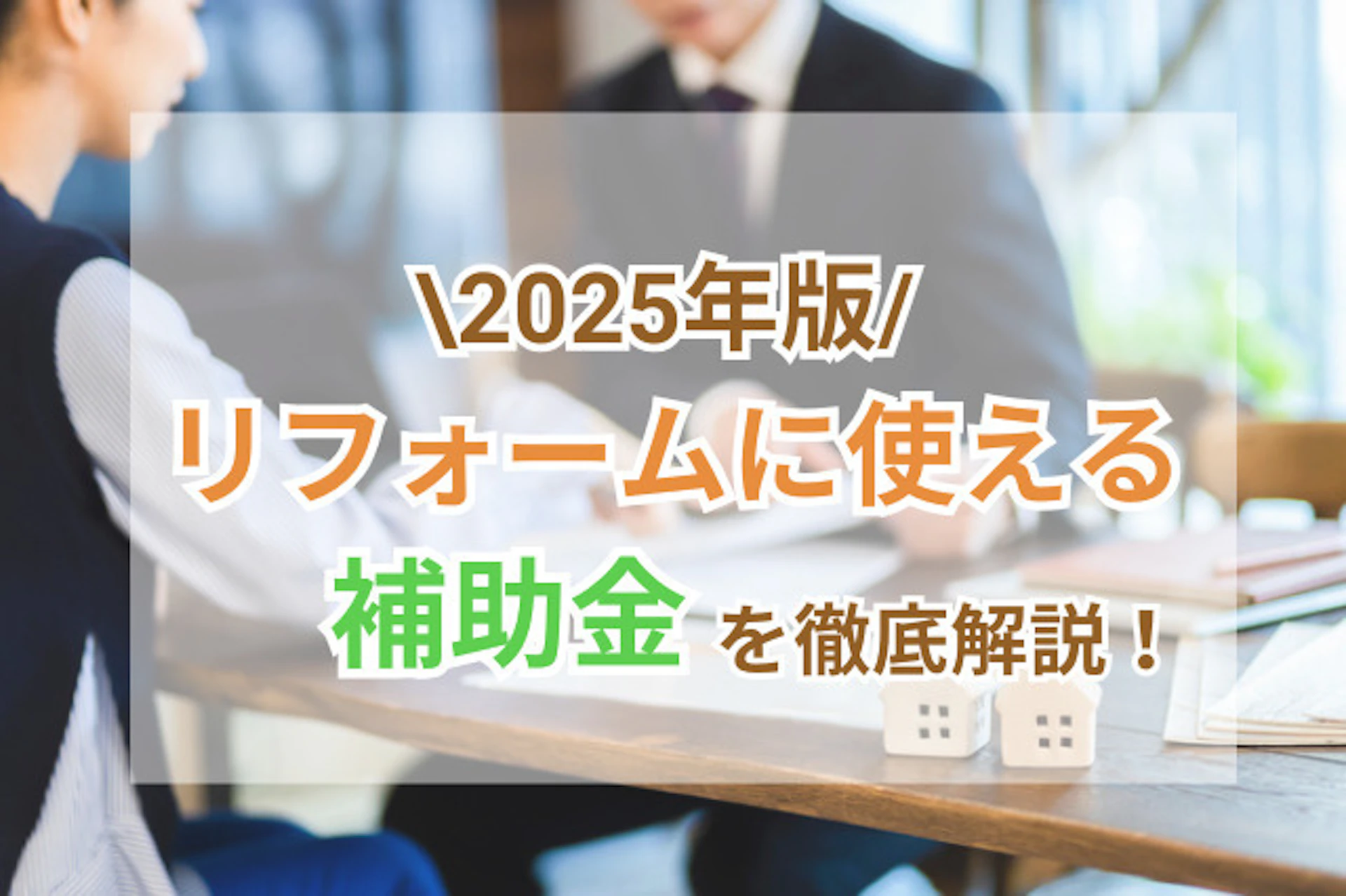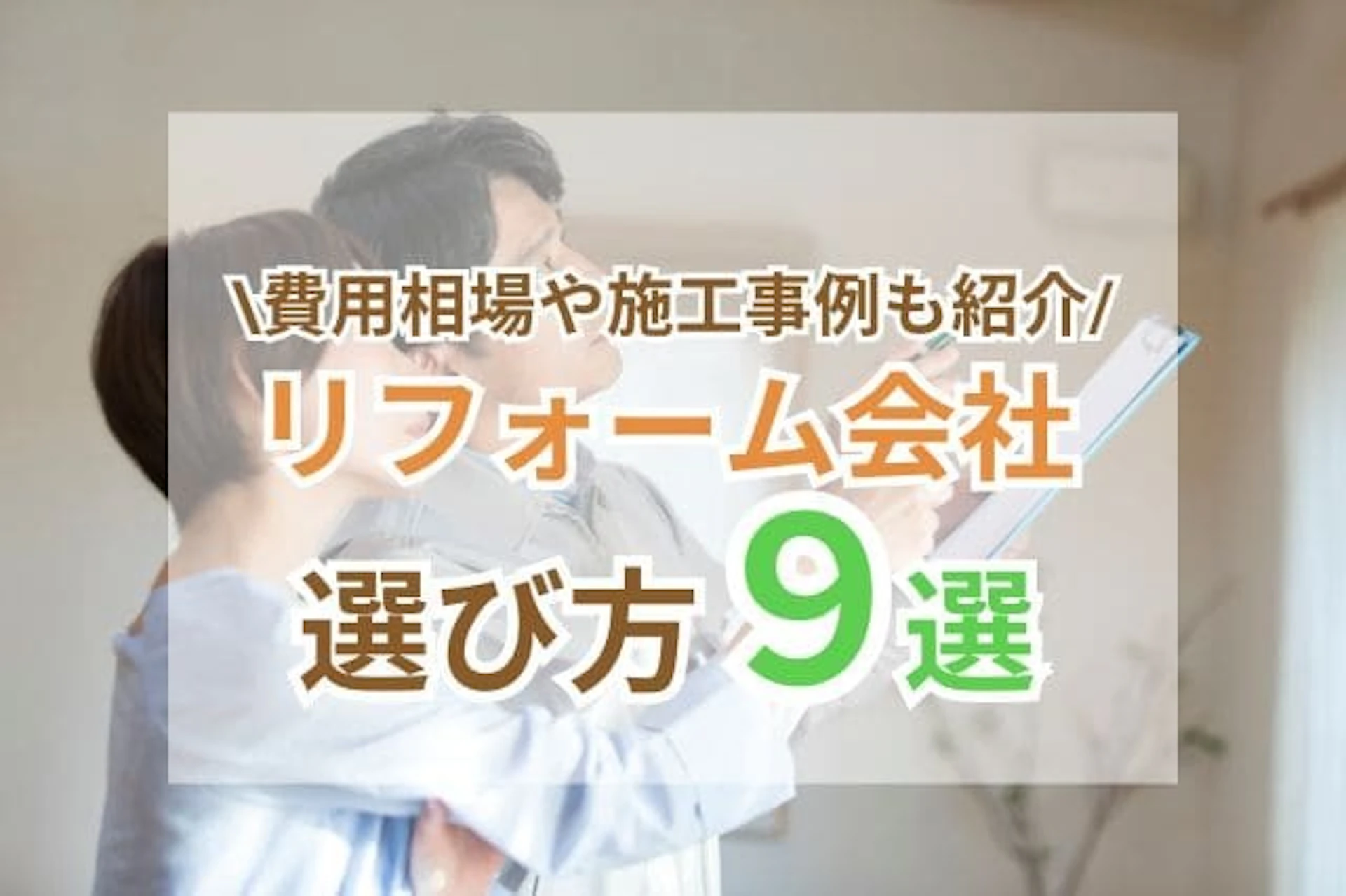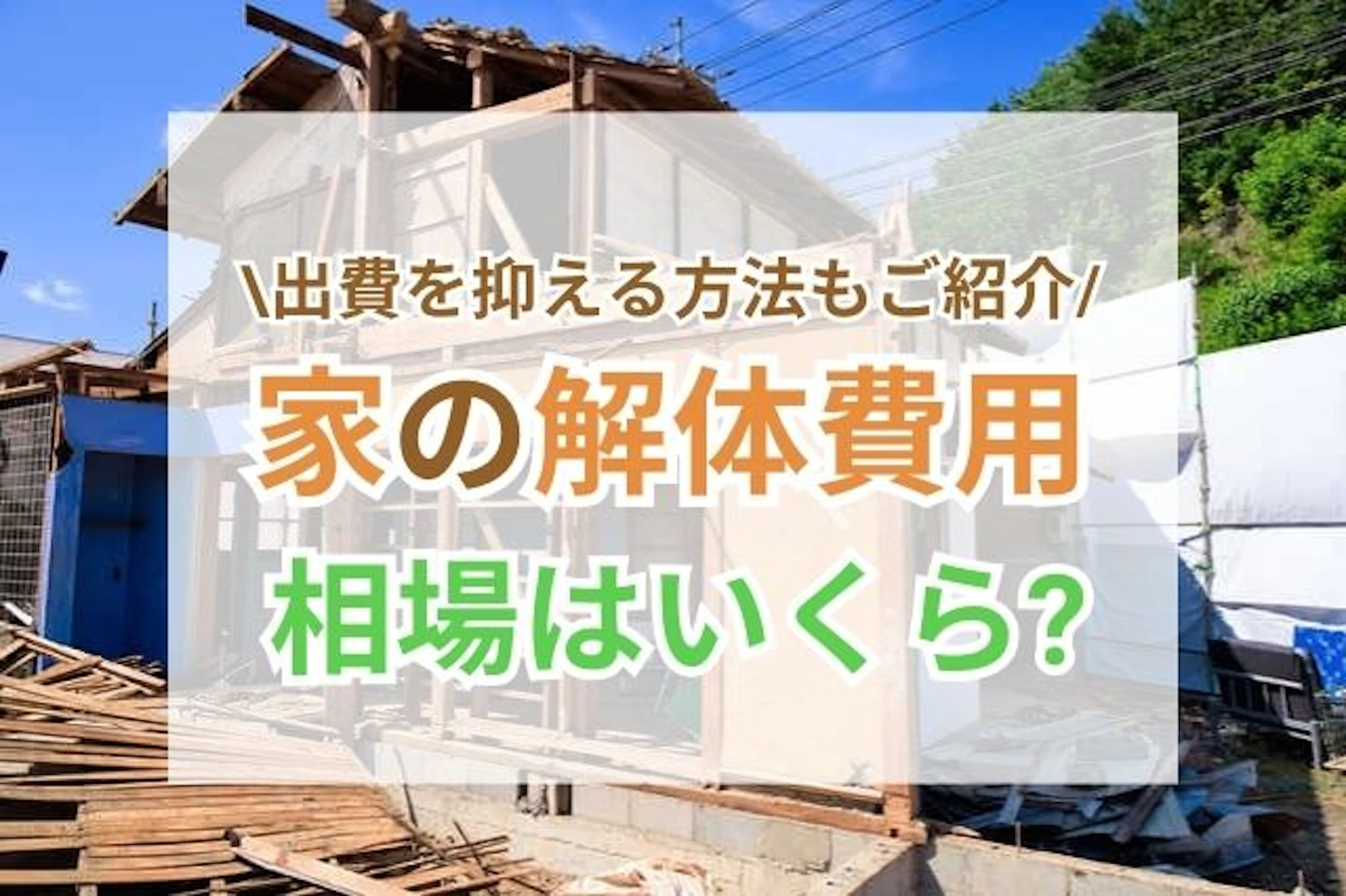ブロック塀撤去の費用相場と注意点 | 補助金で賢く解体
更新日:
地震や台風などの自然災害によって、ブロック塀が倒壊する事故が相次いでいます。安全性に不安を感じながらも、撤去費用や工事の進め方が分からずお困りの方もいるのではないでしょうか。 ブロック塀の撤去費用は、自治体の補助金制度を利用すれば、費用負担を抑えられます。この記事では、標準的な費用相場、補助金申請のポイント、信頼できる業者の選び方を解説します。
目次
ブロック塀の撤去費用相場
ブロック塀の撤去費用は、1㎡あたり3,300〜15,000円です。
地域や施工条件などによって異なりますが、目安としては5,000〜10,000円程度の費用だと考えてよいでしょう。
工事の日数
ブロック塀の撤去工事にかかる日数は、1〜3日が目安です。
規模や条件によっては5日〜1週間程度かかる場合もあります。
なお工事の前に、現場調査や事前準備などの段階を経て進められます。
まず、専門業者が現地を訪問し、ブロック塀の状態や周辺環境、搬出経路などを確認します。
工事計画書の作成後、近隣住民への工事説明や必要な許可申請などの準備を進めます。
見積書の各項目を理解して適正価格を見極めるコツ
ブロック塀撤去の見積書を正しく理解するには、主要な費用項目の内訳と標準的な割合を把握することが大切です。
一般的な見積書には、次の基本項目と追加項目が含まれます。
基本工事費 | 撤去作業の人件費と重機代 |
|---|---|
廃材処分費 | 産業廃棄物の運搬・処理費用 |
諸経費 | 現場管理費や一般管理費など |
複数の見積書を比較する際は、基本項目の金額と割合が相場から大きく外れていないかを確認しましょう。
>> リフォーム見積書のチェックポイント!わかりづらい諸経費も解説
現場の状況によって必要となる追加費用には、隣地との境界に設置する防護ネットなどの養生費用、大型重機の使用料、交通量の多い道路に面している場合の交通誘導員配置費用などがあります。
ブロック塀の撤去工事に詳しい 施工業者を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼
危険なブロック塀撤去を後押しする補助金制度と申請方法
ブロック塀の倒壊事故を防ぐため、多くの自治体で撤去工事への補助金制度があります。
ここでは、申請から補助金受け取りまでの手順や、申請時の注意点をご紹介します。
住宅耐震化支援事業で受けられる補助金の内容
補助金の申請には、次の要件を満たす必要があります。
- 道路に面した高さ1m超えのブロック塀である(地域により異なる)
- 耐震診断で危険と判定された建築基準法に適合しない構造である
- 工事着手前に申請を行い、必要書類をすべて提出する
- 施工業者による適切な見積書を添付する
- 工事完了後、撤去状況を示す写真などの完了報告を提出する
申請する際は、まず自治体の担当窓口に相談し、現地調査を依頼しましょう。
調査結果に基づき、ブロック塀の危険度や補助金の対象となるかを判断します。
工事に着手する前に、施工業者の選定や見積書の取得など、必要な準備を整えておくことが重要です。
工事完了後は速やかに完了報告を行い、補助金の請求手続きを進めましょう。
自治体別の補助上限額と対象工事の条件
ブロック塀撤去の補助金制度は、自治体によって補助上限額や対象条件が異なります。
主要都市の補助制度を比較すると、次の以下のような違いがあります。
自治体 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
大阪市 | 15万円 | 1/2 |
地方都市 | 10~20万円など | 1/2以内など |
補助対象となるブロック塀は、道路に面した高さ1m超えのものなどが基本条件ですが、地域により高さの基準は異なります。
建築基準法に適合していない違法建築物や、老朽化により危険と判断された塀が対象となります。
また、通学路や緊急輸送道路に面している場合は、補助額が上乗せされる自治体も多いです。
例えば、通学路沿いでは補助率が3//4に引き上げられたり、上限額が1.5倍になったりする制度があります。
申請前に必ず、お住まいの自治体の建築課などに相談し、対象要件や必要書類を確認しましょう。
地域や塀の状況によって補助内容が変わるため、事前の情報収集が重要です。
申請から補助金受け取りまでの具体的な手順
補助金申請の手順は、たいていは自治体の窓口やホームページから申請書類一式を入手することから始まります。
申請書とともに、ブロック塀の現況写真や位置図、工事見積書が必要です。
自治体職員による現地調査後、申請書類一式を提出します。
申請から交付決定までは通常2〜4週間程度かかると考えておくとよいでしょう。
交付決定通知を受け取ってから工事に着手できるため、工事業者との日程調整も大切です。
申請から補助金受け取りまでの流れ
申請から補助金受け取りまでの流れは次の通りです。
手順 | 必要書類・作業内容 |
|---|---|
申請時 | 申請書、現況写真、位置図、見積書 |
工事完了時 | 完了報告書、施工前後写真、領収書 |
補助金受取 | 口座情報、印鑑証明書(必要な場合) |
工事完了後、完了報告書に施工前後の写真や領収書を添えて提出します。
書類審査後、申請時に指定した口座に補助金が振り込まれます。
振込までの期間は自治体によって異なりますが、おおむね1〜2ヶ月程度です。
申請時によくある不備と対処法を事前確認
補助金申請の不備による交付遅延や対象外判定を防ぐため、申請時の注意点を確認しておきましょう。
特に多い不備とその対処法をまとめました。
申請書類の記載漏れ | 工事場所の住所、塀の寸法、工事内容の詳細など、すべての項目を正確に記入し、必要に応じて図面や写真を添付 |
|---|---|
工事着手時期の誤り | 必ず交付決定通知を受けてから工事を開始(事前着工は補助対象外) |
添付書類の不足 | 建物の登記簿謄本、施工業者の見積書、現況写真などを準備 |
工事完了報告の不備 | 施工前・施工中・完了後の写真、領収書原本、施工証明書など必要書類を完備 |
施工業者との認識違い | 工事内容、撮影ポイント、必要書類について事前に詳細を打ち合わせ |
不明点がある場合は、必ず自治体の担当窓口に相談してください。
書類の事前確認で、スムーズな補助金交付につながります。
また、工事の記録写真は施工業者任せにせず、施主側でも撮影しておくと安心です。
ブロック塀の撤去工事に詳しい 施工業者を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼
信頼できるブロック塀解体業者の探し方

ブロック塀の解体工事は、実績のある業者選びが重要です。
本章では長期的な視点で安心できる業者の特徴を解説していきます。
優良解体業者の必須資格と施工実績の見方
信頼できる解体業者を選ぶには、まず法的資格の確認が不可欠です。
「解体工事業登録票」を保有しているか、そしてそれらの登録番号と有効期限を確認しましょう。
施工実績は、おおよそ過去3年以内のブロック塀撤去工事を中心に確認します。
この際、近隣地域での実績や、自宅と似た条件での施工例をチェックするのがおすすめです。
また、実績件数だけでなく、施工写真や完工事例の詳細な記録を求めることで、業者の技術力を把握できます。
見積書の比較ポイント
見積書の内訳を詳しく確認することで、適正価格での工事実施が可能になります。
見積書には、養生シート、重機使用料、交通誘導員の人件費など、追加費用の発生要因が明確に記載されているか確認が必要です。
特に重機が必要な場合は、搬入出費用や使用料が大きく変動する可能性があります。
最低でも3社以上から見積りを取得し、施工条件による価格差を比較検討しましょう。
相場から大きく外れた見積額や、根拠が不明確な費用項目がある場合は注意が必要です。
近隣トラブルを防ぐ工事手順と配慮事項
ブロック塀の解体工事では、周辺環境や近隣住民への影響が大きくなりやすいため、配慮と丁寧な説明が不可欠です。
工事開始前に実施すべき配慮事項をまとめました。
- 工事計画書の作成と近隣への事前説明(工期・作業時間・騒音レベルなど)
- 工事車両の進入経路と駐車位置の明確化
- 資材置き場の適切な配置と歩行者の安全確保
- 防塵シートの設置による粉塵飛散防止
- 低騒音・低振動型機械の使用
作業時間は通常8~17時までとし、近隣の生活リズムに配慮した工程を組むことが推奨されます。
また、工事期間中は現場責任者の連絡先を明示し、住民からの問い合わせにも対応できる体制を整えましょう。
解体後の廃材処理についても、産業廃棄物の適正処理を徹底し、搬出時の騒音や道路の汚れにも注意を払う必要があります。
アフターフォローが充実した業者の特徴
信頼できる解体業者は、工事完了後もサポート体制が整っています。
次のようなアフターフォロー体制が整っている業者を選びましょう。
- 施工後3か月、6か月、1年などでの無償点検と報告書の提出
- 地震や台風後の緊急点検サービスと24時間対応窓口の設置
- 撤去跡地の活用提案や代替フェンスの設置相談
- 施工箇所の写真記録の保管と定期的な状態確認
- 近隣とのトラブル発生時の窓口対応
特に地震や台風で不具合が生じた場合、迅速な現場確認と対策提案ができる体制があるか事前に確認しましょう。
ブロック塀撤去後の敷地活用について、提案やアドバイスができる業者であれば、将来的な土地の有効活用にも役立ちます。
ブロック塀撤去に詳しい専門業者に工事を依頼しよう
ブロック塀の撤去は、安全性と費用対効果を考慮して判断しましょう。
補助金制度を活用することで費用を抑えられる場合があります。事前に相場や必要な手続きを理解しておくことが大切です。
施工業者の選定や近隣への配慮など、注意点を押さえることで、安全かつスムーズな撤去工事が実現できます。
ブロック塀の撤去工事に詳しい 施工業者を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼