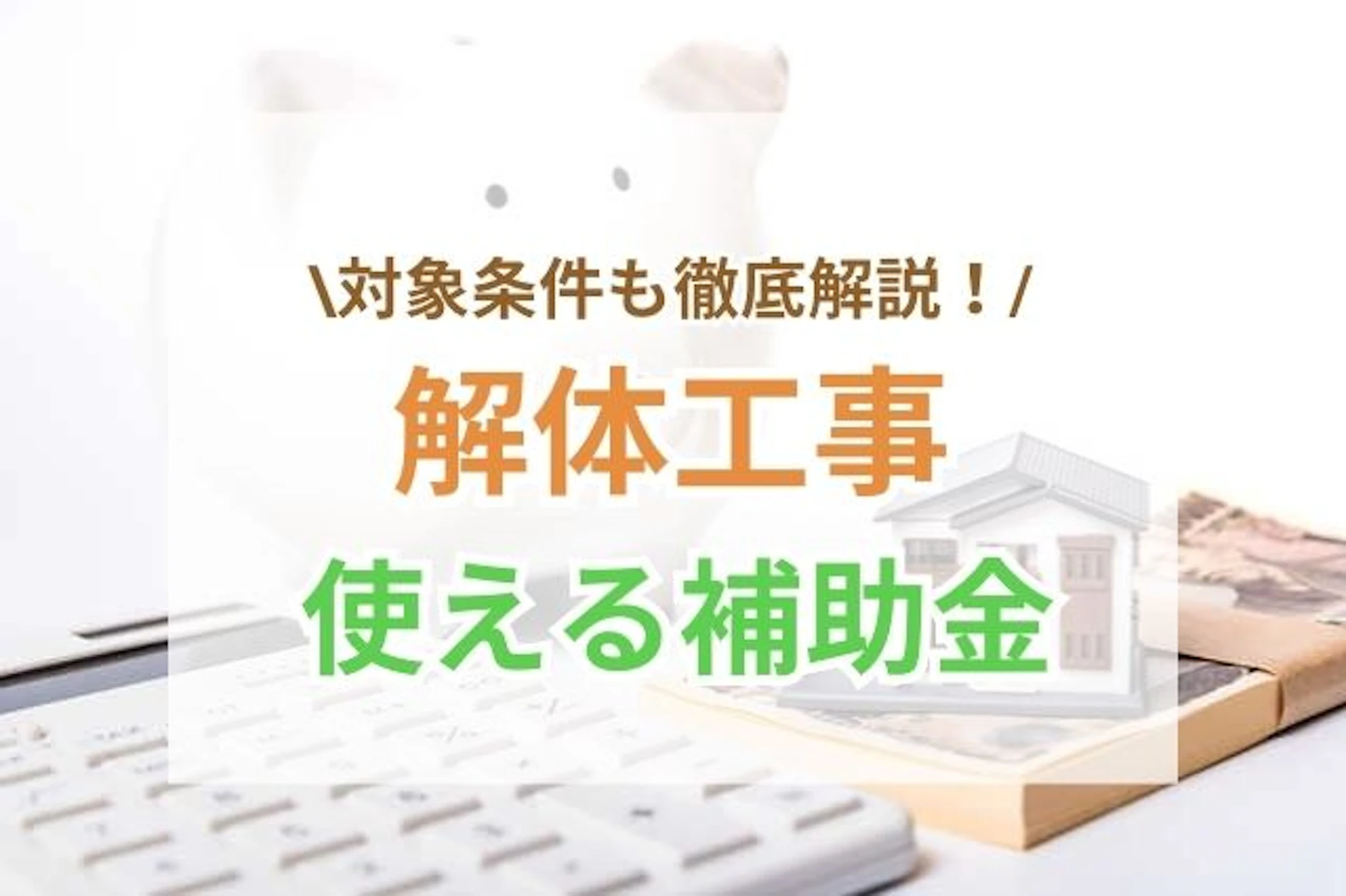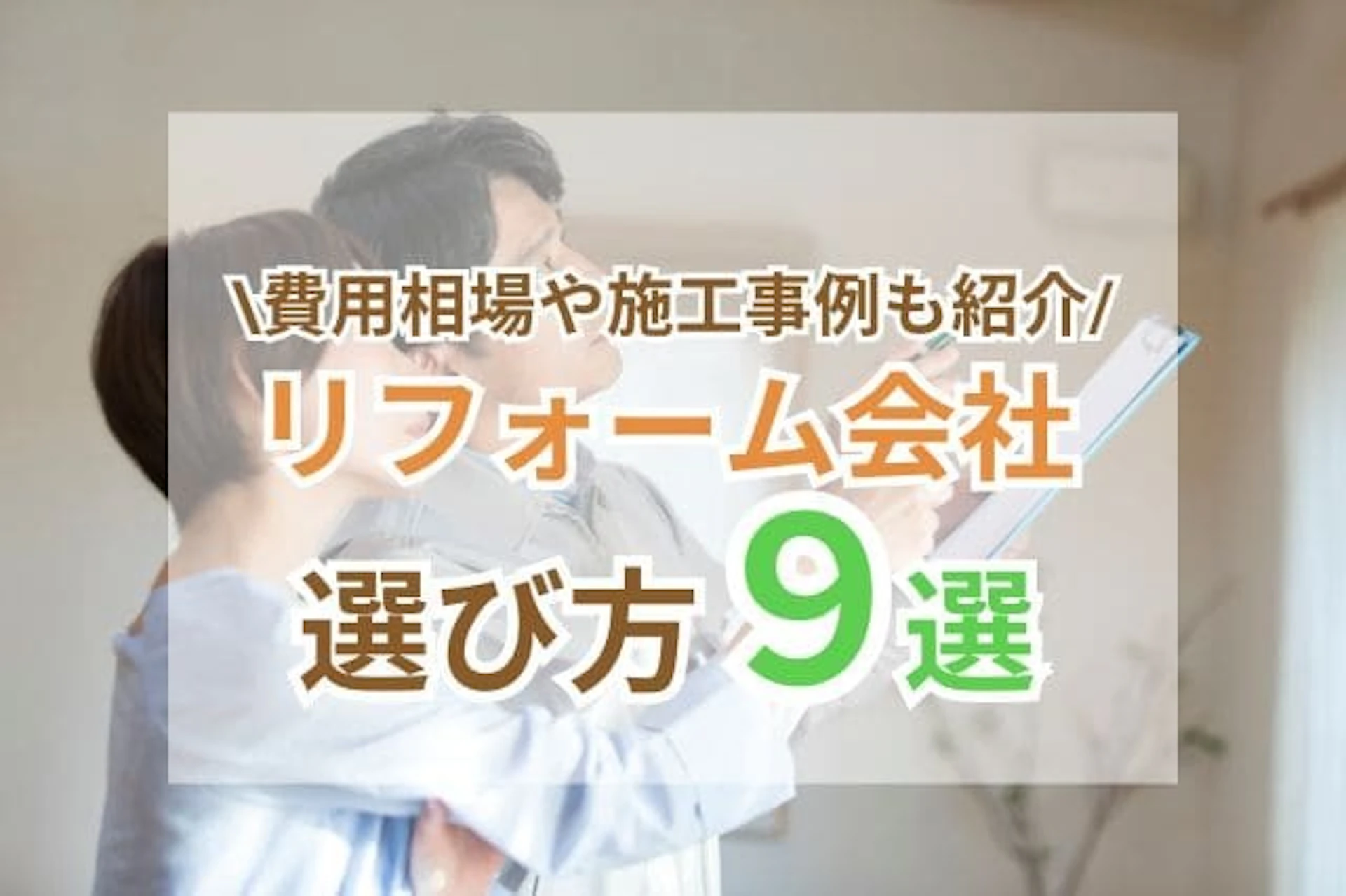古家付き土地は売却する?更地にする?解体の費用相場や注意点を徹底解説
更新日:
築年数の古い家が建っている土地を売却できるのか不安な人も多いでしょう。近年は、リフォーム・リノベーション住宅の需要の高まりに伴い、古家を残したまま売却する人が増えています。 本記事では、古家付き土地を売却する際のメリット・デメリットや、解体にかかる費用、注意点について解説します。最後まで読めば、所有している古家付き土地を売却するべきか、更地にするべきかも判断できるので、ぜひ参考にしてください。
目次
古家付き土地とは?更地との違い

「古家付き土地」とは、「古い建物がある土地」を指します。
「古家付き土地」と「中古住宅」とで明確な違いはありませんが、一般的には築20年を超える家が建っている場合に、「古家付き土地」と表記されることが多いようです。
古家付き土地は建物自体に経済的価値はなく、実質、土地のみの価値で売却します。
一方、古家を取り壊して土地を「更地」にして売却する方法もあります。
更地とは、建築物や構造物が何もなく、土地を購入したらすぐに新しい建物を建てられる状態の宅地です。
古家付き土地をそのまま売却するメリット

古家付き土地としてそのまま売却するメリットは主に以下の2つです。
● 解体費用がかからない
● 売れるまでの期間も固定資産税が軽減される
解体費用がかからない
古家付き土地を売る場合、解体から整地までの費用は原則として買主が負担します。
つまりそのまま売ることで、更地にする費用負担が軽減できるのです。
解体費用は建物の構造や地域によって異なります。
木造の家で坪単価3~5万円程度が相場です。
例えば、50坪の木造住宅の解体費用は150~250万円ほどになります。
古家付き土地をそのままの状態で売却するのであれば、解体費用を負担せずに済むでしょう。
売れるまでの期間も固定資産税が軽減される
住宅や土地を所有すると、1年に1回自治体に住宅と土地の固定資産税を納めなければいけません。
しかし土地に住宅が建っている場合、以下のよう「住宅用地に係る特例」が適用され、土地の固定資産税は減税されます。
【住宅用地に係る特例】
区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 課税標準額 |
|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 価格×1/6 |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 価格×1/3 |
出典:「資料(税負担軽減措置関係)」(総務省)を加工して作成
古家付き土地として売りに出すと、土地の固定資産税の負担が軽減されたままになるため、安心して売却活動を行えるでしょう。
更地にした場合は、「住宅用地に係る特例」が適用されませんので注意してください。
施工実績が豊富な 解体業者に相談したい!無料解体業者一括見積もり依頼
古家付き土地をそのまま売却するデメリット
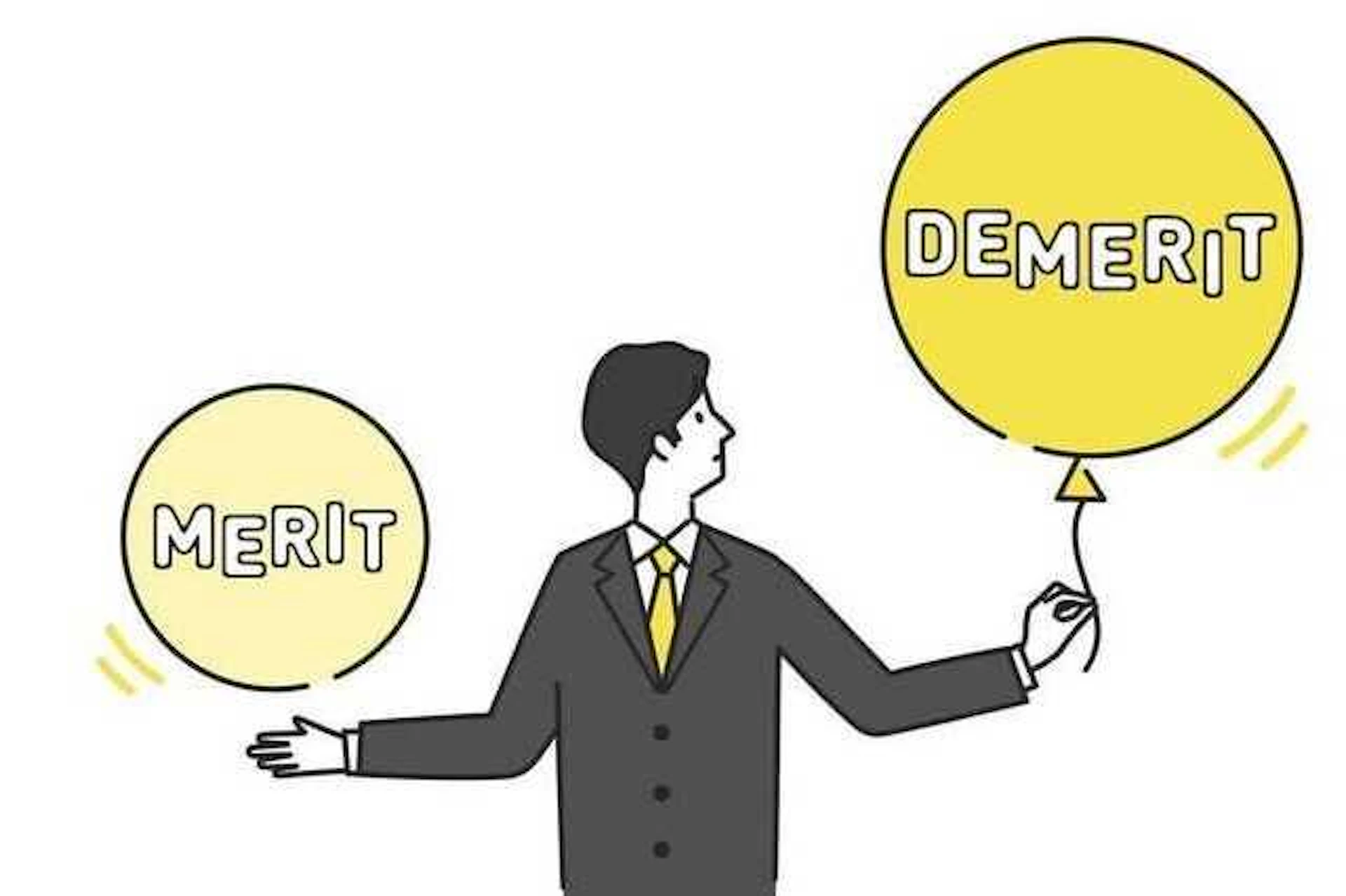
古家付き土地をそのまま売却するデメリットは次のとおりです。
● 売却価格が安くなる傾向がある
● 契約不適合責任を負うことがある
● 買い手が見つかりにくい
メリットだけではなく、デメリットも知った上で売却を検討しましょう。
売却価格が安くなる傾向がある
古家付き土地の場合、市場価格よりも売却価格が安くなる傾向があります。
古家付き土地のまま売却するケースでは、解体費用やそれに伴う手間を負担するのは買主です。
そのまま住む場合でも、買主がリフォーム代を負担することになる上、住み始めるまでに時間もかかります。
そのため、買主の負担分を見込んだ価格設定が求められるのです。
古家付きで売却する場合には解体費用や工事の手間が省けるメリットがある一方で、更地価格よりも売却価格が安くなることを理解しておきましょう。
契約不適合責任を負うことがある
買主が建物を解体せずにそのまま居住する場合、契約不適合責任を負うリスクが生じます。
契約不適合責任とは、土地の売却後に売主の知らない不具合が生じたときに、売主が補修費用や損害賠償を支払うルールのことです。
シロアリ被害や地中埋設物なども、売主の責任対象になります。
古家付き土地の状況を把握しないまま売却すると、売却後に損害賠償を請求されるリスクがあるので注意が必要です。
ただし契約不適合責任は以下の場合に限り、免責できます。
● 買主が不適合を知ったときから1年以内に売主にその旨を通知しない場合
● 買主の了承の上、契約不適合責任を免責する契約を交わした場合
古家付き土地の売却時は、契約書面で契約不適合責任を免責するなどの対策を検討しましょう。
買い手が見つかりにくい
一般的に古家付き土地は、更地よりも売却しにくいとされています。
建物の状態がよくない場合は、建物が残っていることで土地活用の自由度が下がり、土地の用途が限られるためです。
さらに建物が残っていると土壌調査や地下埋没物の有無、汚染調査などがしにくく、買主に土地の情報提供ができません。
そのため、信頼度が下がってしまいます。
古すぎる場合は見た目にもマイナスイメージを持たれてしまう点も、買い手が見つかりにくい原因です。
施工実績が豊富な 解体業者に相談したい!無料解体業者一括見積もり依頼
古家付き土地をそのまま売却した方がいいケース

古家付き土地を売却する際、建物を残したまま売却した方がいいケースとはどのような場合なのでしょうか。
建物に利用価値がある
古くても問題なく住める建物であれば、古家付き土地として売却するのがおすすめです。
買主がそのまま居住したり、購入後に賃貸物件としても活用したりが可能になります。
古民家として利用できる建物や、伝統的な工法が施された建物は価値があるため、古家付き土地として売却しやすくなるでしょう。
近年では建築技術も高まり古家のリフォームが可能になりました。
それに伴い、古家を購入してリフォーム・リノベーションをする人が増加しています。
再建築がむずかしい
更地にした後に新たに建物を建てることができない土地を「再建築不可物件」といいます。
1981年に改正された建築基準法では、以下を再建築不可物件と定めています。
● 前面道路が建築基準法で定められた道路ではない
● 接道部分が2m未満の物件
再建築不可物件や都市計画区域にある建物は、既存の建物を解体すると新たに建物を建築できません。
古家を壊さずに売却するのがおすすめです。
再建築不可物件は新築はできませんが、リフォームは可能です。
立地や条件によっては、リフォームをすることで住宅としての利用価値が高くなる場合もあるでしょう。
解体費用が土地の査定価格よりも高い
不動産会社による土地の査定価格よりも解体費用が高くなってしまう場合も、古家を残したまま売却した方がいいでしょう。
解体業者に見積もりを取る際は2~3社に相見積もりを取り、比較するのをおすすめします。
複数業者の見積もりを取るなら、一括で見積もり依頼ができるリショップナビが便利です。
古家付き土地を更地にした方がいいケース

ここからは、古家を解体して更地で売却した方がいいケースをご紹介します。
建物が老朽化している
建物が古すぎる場合は、建物の利用価値が低いため更地にして売却するのをおすすめします。
一般的に建物には、構造や用途によって耐用年数が定められています。
耐用年数を指標として、建物が老朽化しているか否かを判断できるでしょう。
以下の表は、住宅の構造別の耐用年数を表しています。
構造 | 耐用年数 |
|---|---|
木造・合成樹脂造 | 22年 |
木骨モルタル造 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
れんが造・石造・ブロック造 | 38年 |
金属造 | 19~34年※骨格材の肉厚による |
出典:「主な減価償却資産の耐用年数表 」(国税庁)を加工して作成
もちろん耐用年数を超えた建物でも住むことは可能ですが、不動産価値はなくなります。
建物が老朽化している場合には、解体を検討しましょう。
建物の耐震性が低い
更地にして売却するかを判断するときに、「1981年(昭和56年)6月以前の建築物」かどうかも基準になります。
1981年6月以前の建築物は、旧建築基準法の耐震基準によって建築確認申請が行われていました。
旧耐震基準の建築確認を受けた建物は、現在の耐震基準にしたがって建てたものに比べて、耐震性が低い恐れがあります。
また、1981年以前の建築物は、すでに築年数が41年以上と老朽化しているため、解体をおすすめします。
解体費用がかかっても早く売却したい事情がある
解体費用がかかっても早く売却したい人は、更地にしてからの売却を検討しましょう。
更地にした場合、買主にとって土地利用の用途が広がるため、早く売却されやすくなります。
また、売却前の古家にかかる管理費を負担したくない人も同様に、更地するのがおすすめです。
古家はすぐに買い手がつかないため、売却期間が長くなりがちです。
その間も定期的な掃除や点検などの維持費の負担が発生します。
遠方に住んでいる場合には、さらに時間や労力がかかります。
古家の面倒な管理から解放されたい人は更地にしましょう。
施工実績が豊富な 解体業者に相談したい!無料解体業者一括見積もり依頼
古家の解体にかかる費用相場

古家の解体費用は、築年数や老朽具合には関係なく建物の構造や面積、立地の条件などによって異なります。
解体費用のおおまかな相場は、以下を参考にしてください。
構造 | 1坪当たりの費用相場 |
|---|---|
木造 | およそ3~5万円 |
鉄骨造 | およそ4~6万円 |
鉄筋コンクリート造(RC) | およそ6~8万円 |
一般的な30坪の木造家屋の場合、90万~150万円ほどかかるでしょう。
また、接道の状況や近隣宅との距離などでも費用は変動します。
以下の場合は、特に費用が高くなる傾向があるので確認しておきましょう。
● 住宅密集地で、重機や廃棄物処理のトラックが搬入できず、手作業が増える場合
● 庭や倉庫、ブロック塀、古井戸などの付帯物がある場合
解体費用のほかに、減失登記費用もかかります。
減失登記は建物を解体してから1ヶ月以内に申請しなければなりません。
減失登記をせずにいると、10万円以下の罰金や固定資産税の継続のリスクが発生します。
減失登記申請を素人が行うのは困難なため、土地家屋調査士や司法書士に依頼するのが一般的です。
その場合、5万円前後の費用がかかります。
古家付き土地の売却で発生する税金

古家付き土地を売却した際に発生する税金について解説します。
譲渡所得税
譲渡所得税は、個人が不動産を売却して譲渡所得(売却益)が発生したときにかかる税金です。
売却時に利益が出なかった場合には、譲渡所得税はかかりません。
譲渡所得税の計算は、譲渡所得に税率(所有期間によって異なる)をかけて算出します。
譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得=収入金額-取得費用-譲渡費用(-特別控除額)
計算式に必要な費用項目の詳細は、以下に記載します。
収入金額 | 古家付き土地の売却益 |
|---|---|
取得費用 | 売却する古家付き土地を購入したときの費用 |
譲渡費用 | 古家付き土地を売却するために発生した費用 |
ただし、以下の2つの特例に限り、譲渡所得税は特別控除されます。
● マイホームを売ったときの特例:一定条件のもと個人がマイホームを譲渡した場合、譲渡所得が最高3,000万円控除される特例
● 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例:一定条件のもと引き継いだ空き家を譲渡した場合、譲渡所得が最高3,000万円控除される特例
印紙税
古家付き土地の売買では、契約書に貼る印紙代として印紙税が発生します。
印紙税は土地の売却価格によって異なります。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成され、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものは軽減措置が適用され以下の金額になります。
契約金額 | 税額 |
|---|---|
500~1,000万円以下 | 5千円 |
1,000~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万~1億円以下 | 3万円 |
1~5億円以下 | 6万円 |
出典:「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(国税庁)を加工して作成
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で住宅や土地など固定資産を所有する人に課せられる税金です。
居住していなくても所有者と認められれば支払い義務が生じ、自治体から合計額の記載された納税通知書が毎年郵送で届きます。
住宅や土地を売却した場合には、売却した時点までの固定資産税が日割りで清算されます。
古家付き土地を売却する際の注意点

古家付き土地を売却するにあたって、注意しておくべきことを解説します。
売却するときにトラブルにならないよう、以下をしっかり把握しておきましょう。
契約不適合責任をすべて免責する
古家付き土地の売却時には、土地や建物の契約不適合責任をすべて免責しておくことをおすすめします。
契約不適合責任とは、土地や建物に思わぬ欠陥や不具合があった場合、買主から修繕費の請求や損害賠償を求められる責任です。
買主は引き渡しから10年間、契約不適合責任の請求権をもちます。
つまり売主は、最大10年間は損害賠償等のリスクを負うことになります。
買主の了承のうえ、売買契約書に「土地や建物の契約不適合責を負わない」旨の契約を交わす対策を施しましょう。
境界や権利を明確にする
売却前に、土地の境界線を明確にしましょう。
代々受け継いでいる土地では、隣家との境界線があやふやな場合も多くあります。
また実際の境界と、登記簿謄本に記載されている境界とが異なるケースもよくあることです。
境界線を明確にしないまま売却すると、引き渡し後に買主と隣地住民とでトラブルに発展するおそれがあります。
庭木の枝が隣地の敷地に越境しているケースなどもトラブルになりやすいものです。
境界や権利は売却前に明確にして、トラブルを回避しましょう。
残置物を処分しておく
古家付き土地を売却する際、家具や家電などの残置物はなるべく自分で処分しておきましょう。
残置物を自分で処分する場合、一般廃棄物扱いです。
しかし解体業者が処分する場合は産業廃棄物扱いとなり、費用が高くなってしまいます。
自分であらかじめ残置物を処分しておくことで、処分費の削減ができるでしょう。
ただし重たい家具や家電などの場合は、自分で搬出すると身体に負担がかかるため解体業者に依頼するのをおすすめします。
古家付き土地を売却する際は利点や注意点を理解してトラブルを避けよう

古家付き土地を建物を残してそのまま売却する場合、メリット・デメリットをしっかり把握して、所有する古家付き土地をそのまま売却するのか、更地にして売却するのかを検討しましょう。
古家の解体するときは、まずは複数社に見積もりを取るのがおすすめです。
最低3社に相見積もりを取ることで、信頼できる業者が見つかるでしょう。
リショップナビなら複数の業者の一括見積もりが可能です。
最適な業者選びには、リショップナビを活用してください。
施工実績が豊富な 解体業者に相談したい! 無料解体業者一括見積もり依頼
こちらの記事もおすすめ♪
>> アスベストを含む建物の解体工事はどうする?