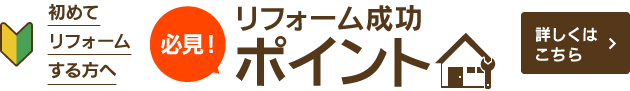シロアリが家に入り込む代表的な経路
シロアリの侵入を防ぐためには、まず彼らがどのような経路で家に入り込むのかを知ることが大切です。
また、ヤマトシロアリとイエシロアリでは侵入パターンが異なるため、種類に応じた対策も必要になります。
|
|
基礎や土台からの侵入
シロアリは地中から蟻道(ぎどう)を作り、建物の基礎にあるコンクリートの継ぎ目やごくわずかなひび割れから住宅内へ入ってきます。
経年劣化で生じた、わずか0.6mm程度という非常に小さな隙間でも、シロアリにとっては十分な通り道になってしまうのです。
最も注意が必要なのは、床下の土台と基礎の間にできる隙間や、ベタ基礎であっても立ち上がり基礎との継ぎ目に生じる微細な隙間です。
これらの箇所は湿気が多く、シロアリが好む環境になりやすいため、格好の侵入ポイントになります。
さらに、基礎断熱材の裏側や配管・配線などの貫通部周辺も主要な侵入ルートとなります。
セパレーター金具周辺やアース線の貫通部など、建築時に問題がなくても経年変化で生じた隙間から侵入するため注意が必要です。
庭や植木鉢から
庭は、意外にもシロアリの侵入経路として見落とされがちな場所です。
植木鉢やプランターの受け皿にたまった水分、朽ちた木材や切り株などは、シロアリにとって格好の餌場となります。
特に注意したいのは、植木鉢を外壁に面して設置しているケースです。
床下の換気口を塞ぐと湿気がこもりやすくなり、シロアリが蟻道を伸ばして基礎の隙間から床下に侵入するリスクが高まります。
庭から建物への侵入パターン
シロアリは土の中にトンネル状の蟻道を作り、花壇やプランターの下から建物へと移動します。
建物の近くに木材や段ボールを置いていると、それが餌となって建物内部へ被害が広がる可能性もあるのです。
庭と建物が近い環境で、ウッドデッキが建物に密着していたり、水はけが悪く湿気がたまりやすかったりする条件が重なると、シロアリにとって住宅への道筋が整ってしまいます。
床下換気口や基礎断熱材周り
床下の換気口は、住宅の湿気を防ぐために欠かせない設備ですが、実はシロアリにとっても格好の侵入経路となってしまいます。
最近の住宅では、基礎の上端と土台の間に換気スペースを確保する方法が一般的です。
この隙間は空気の流れをよくする一方で、シロアリが侵入する通り道にもなり得るのです。
基礎断熱材の周辺も注意が必要な場所です。
施工時の不備や経年劣化で断熱材に隙間や剥がれが生じると、そこからシロアリが侵入する可能性があります。
断熱材の裏側は結露しやすく湿度が高くなりがちで、シロアリが生息しやすい環境が整ってしまうのです。
|
|
木材の直置きや段ボール保管場所
庭や物置に木材を直接置いたり、段ボール箱を長期間保管したりする場所は、シロアリにとって格好の餌場となってしまいます。
木材や段ボールの主成分であるセルロースは、シロアリの重要な栄養源なのです。
特に注意したいのは屋外での保管方法です。
庭や玄関先に放置された木材や段ボールは、雨で水分を含むとシロアリがさらに好む環境になります。
実際に、庭に放置していた段ボールや、押し入れの奥にしまい込んでいた段ボールが、シロアリの食害でボロボロになっていたケースも報告されています。
シロアリはこれらの餌場から蟻道と呼ばれるトンネルを作り、家屋の床下や柱へと侵入経路を広げていきます。
古い本や雑誌なども同様にセルロースを含むため、湿気の多い場所での長期保管は避けることが大切です。
ヤマトシロアリとイエシロアリの侵入経路の違い
ヤマトシロアリとイエシロアリでは、侵入経路や被害の広がり方に大きな違いがあります。
>> ヤマトシロアリとイエシロアリの大きさはどれくらい?種類と階級別の見分け方
ヤマトシロアリは水分を運ぶ能力がないため、湿った場所に巣を作る習性を持っています。
一方、イエシロアリは建物の下や地中に加工した塊状の大きな巣を作り、さらに分巣(ぶんそう)も増やしていきます。
地中深くから長い蟻道を伸ばし、建物全体に広範囲の食害をもたらす力を持っています。
| 種類 | 侵入パターン | 被害の特徴 |
|---|---|---|
| ヤマトシロアリ | 床下土台周辺から短距離侵入 | 局所的な被害 |
| イエシロアリ | 地中から長距離蟻道形成 | 建物全体への広範囲被害 |
このように侵入パターンが異なるため、種類に応じた適切な対策が重要です。
\専門の業者へ相談したい!/
施工業者の紹介を依頼 ▶
家の中で被害が起きやすい場所

シロアリは、家の中でも特に被害を受けやすい場所があります。
湿気が多く木材が豊富な環境を好むシロアリにとって、水回りや収納スペースは絶好の標的となるのです。
湿気の多い水回り周辺
シロアリにとって、水回りの周辺は最も侵入しやすい場所の一つといえるでしょう。
浴室や洗面脱衣所は湿気がこもりやすく、シロアリが蟻道を作りやすい環境だからです。
特に注意したいのは配管の貫通部分です。
ガス管やPF管、アース線などが基礎を貫通する箇所に隙間があると、そこからシロアリが侵入してしまいます。
水道管や排水管から水漏れが発生している場合は、さらにシロアリが好むジメジメとした環境を作り出してしまうのです。
水回りが狙われる理由
湿気のある床下や、浴室、トイレ、台所など水をよく使う場所は湿気がたまりやすく、シロアリの発生源になりやすい特徴を持っています。
水回りは腐食が進みやすい場所でもあり、床下の木材が湿気で腐ると、シロアリにとって餌と住処を同時に提供する理想的な環境になってしまうのです。
押し入れや畳の下
押し入れや畳の下は、シロアリにとって理想的な住環境になりがちです。
押し入れは暗くて空気の流れが少なく、湿度が上がりやすいという特徴があります。
古い本や衣類に含まれるセルロースがシロアリの餌となり、特に段ボールで保管された本などは格好の標的になってしまうでしょう。
畳の下も同様に危険な場所といえます。湿気が多く暖かい畳は、シロアリにとって非常に好都合な環境になりやすいです。
床下から蟻道を通って侵入したシロアリは、畳下の床板や根太を食害し、さらに畳のイグサや稲わらまで被害を広げていきます。
被害の拡大パターン
シロアリは地面の下から蟻道を伸ばして床下に侵入し、その後床材を経て部屋の中まで食害を広げていきます。
畳に到達する頃には、すでに床下の木材の大部分が食べられている可能性も高いため、早期発見が何よりも重要です。
\専門業者に相談したい!/
施工業者の紹介を依頼 ▶
侵入を防ぐためにできる工夫
シロアリの侵入を完全に阻止するのは難しいものの、適切な対策で被害のリスクを大幅に軽減できます。
湿気の管理と専門業者との連携が、効果的な予防の鍵となります。
日頃からできる環境づくりと、プロの力を借りた定期的なチェック体制を整え、安心して住み続けられる我が家を維持していきましょう。
湿気対策
シロアリは湿気の多い環境を好むため、住まいの湿度管理がとても重要です。
室内の湿度を60%以下に保つことで、シロアリにとって住みにくい環境を作れるでしょう。
エアコンの除湿機能や除湿機を活用し、特に梅雨時期や湿度の高い日は積極的に除湿を行いましょう。
水回りの配管からの水漏れや雨漏りがある場合は、速やかな修繕が大切です。
放置すると建物内部に水分がたまり、シロアリが好む環境を作ってしまいます。
床下の換気対策も欠かせません。
床下換気口の前に物を置かず、風通しをよくすることで湿気を排除できます。
床下換気扇を設置すれば、強制的に空気の流れを生み出し、シロアリの発生を抑えやすくなるでしょう。
早めの業者点検・相談で安心につなげる
シロアリ対策では、専門業者との連携が何よりも重要になります。
シロアリの生態や侵入経路を熟知した業者による年1回の床下点検で、蟻道や木部の食害を早期に発見できます。
もしシロアリの痕跡を見つけた場合、市販の殺虫剤を使うのは避けましょう。
かえって被害を拡大させる恐れがあるため、速やかに専門業者へ連絡し、適切な駆除と薬剤処理を依頼することが大切です。
長期的な予防体制の構築
効果的なシロアリ対策は、一度きりで終わるものではありません。
5年ごとの予防薬剤の再処理や定期メンテナンス契約を結ぶと、長期的な被害防止効果を維持しやすくなります。
業者による専門的な防蟻(ぼうぎ)処理を併用することで、さらにシロアリ対策を強化できます。
シロアリがどこから侵入するかを知り、徹底対策を
シロアリの侵入経路は、床下や基礎部分からが比較的多く、湿気の多い場所や木材が直接土に触れている箇所は特に注意が必要です。
定期的な点検と適切な湿度管理、そして早期発見が被害を抑える鍵となるでしょう。
日頃から家の周りをチェックし、気になる兆候を見つけたら専門家に相談することをおすすめします。
\専門業者に相談したい!/
施工業者の紹介を依頼 ▶

 リショップナビは3つの安心を提供しています!
リショップナビは3つの安心を提供しています!
-

ご希望にあった会社をご紹介!
お住まいの地域に近く・ご希望のリフォーム箇所に対応が可能という基準を元に、厳選した会社をご紹介。可能な限り、ご要望にお応えできるように対応致します。
-

しつこい営業電話はありません!
紹介する会社は、最大で5社まで。また、連絡を希望する時間帯をお伝え頂ければ、しつこい営業電話をすることはありません。
-

見積もり後のフォローも致します
ご紹介後にご不明点や依頼を断りたい会社がある場合も、お気軽にご連絡ください。弊社から各会社へのご連絡も可能となっております。


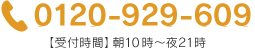
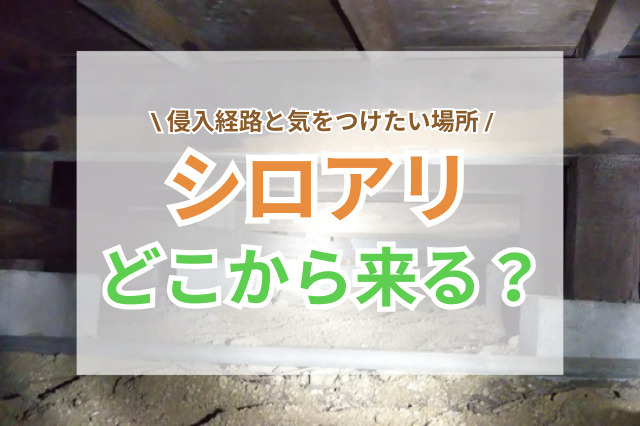
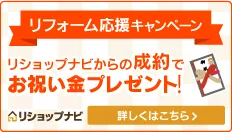

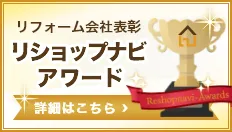
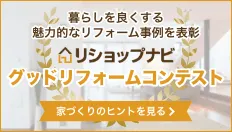

 ピックアップ記事
ピックアップ記事



 お住いの地域で会社を探せます。
お住いの地域で会社を探せます。
 豊富なリフォーム事例を公開中!
豊富なリフォーム事例を公開中!
 シロアリ調査で失敗しない!被害防止の鉄則...
シロアリ調査で失敗しない!被害防止の鉄則...
 シロアリ被害の末期症状とは?|今すぐ対策...
シロアリ被害の末期症状とは?|今すぐ対策...
 シロアリ駆除&予防の費用相場!診断・調査...
シロアリ駆除&予防の費用相場!診断・調査...
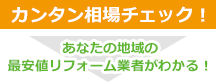
 お役立ちのおすすめ記事
お役立ちのおすすめ記事